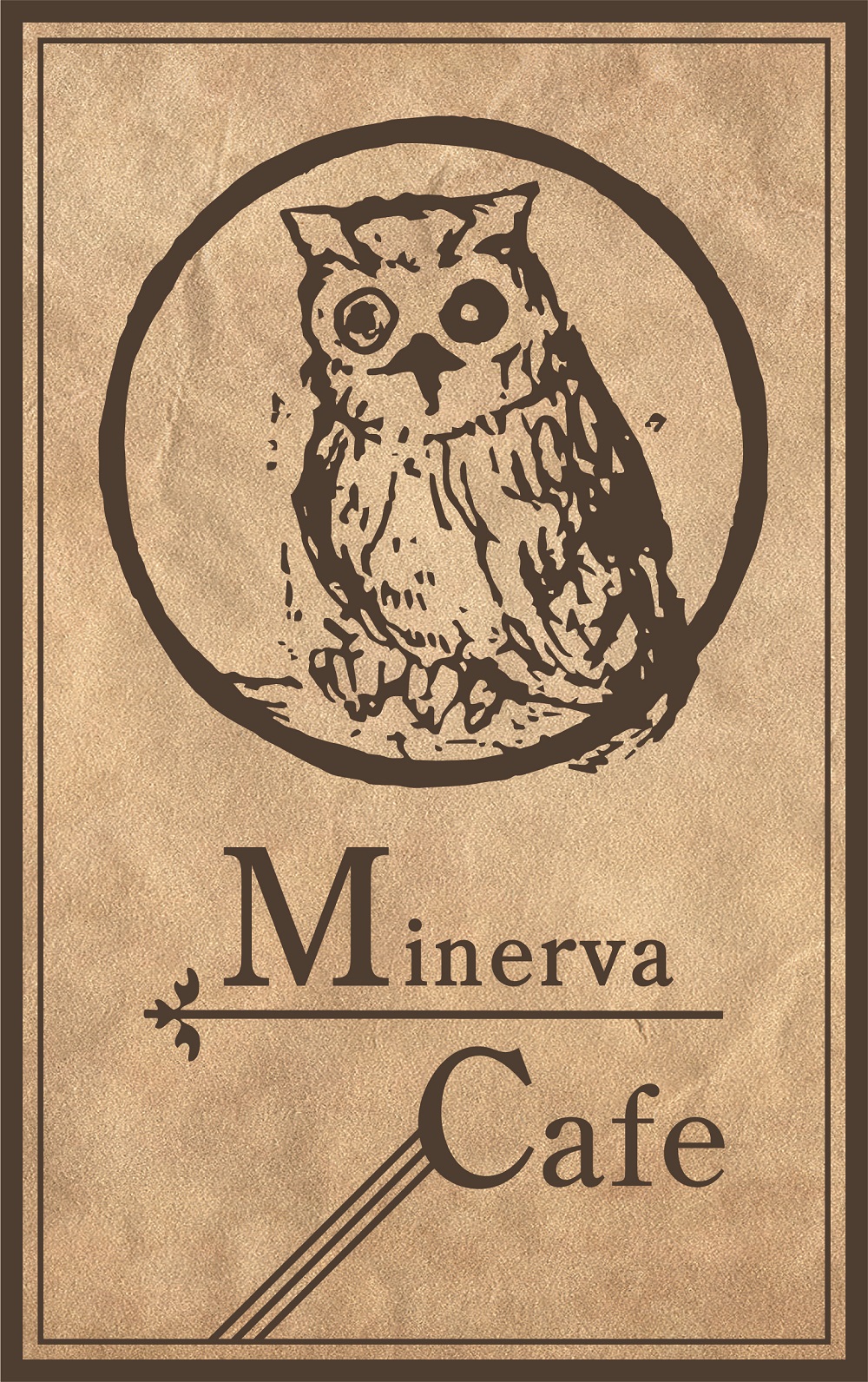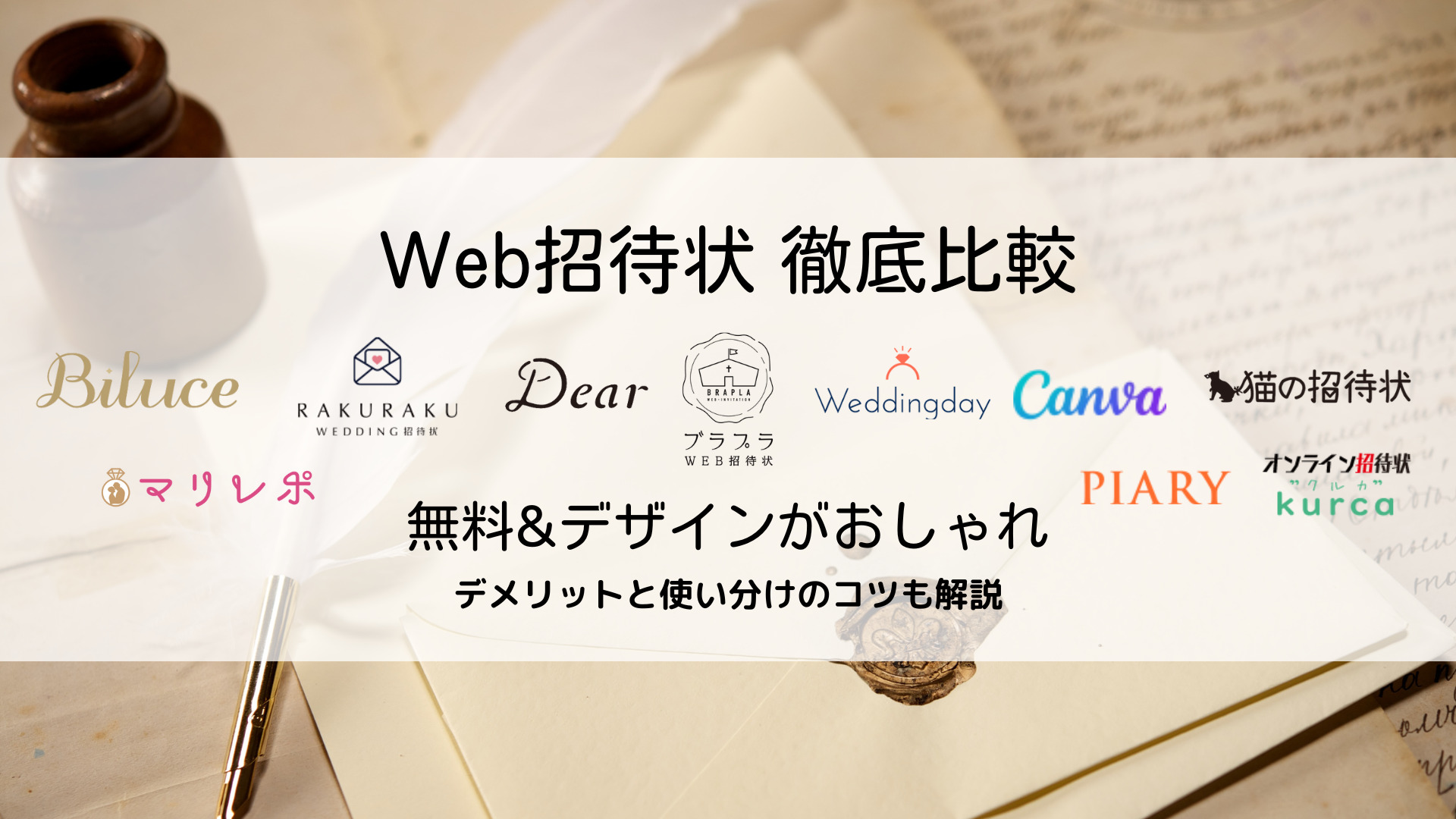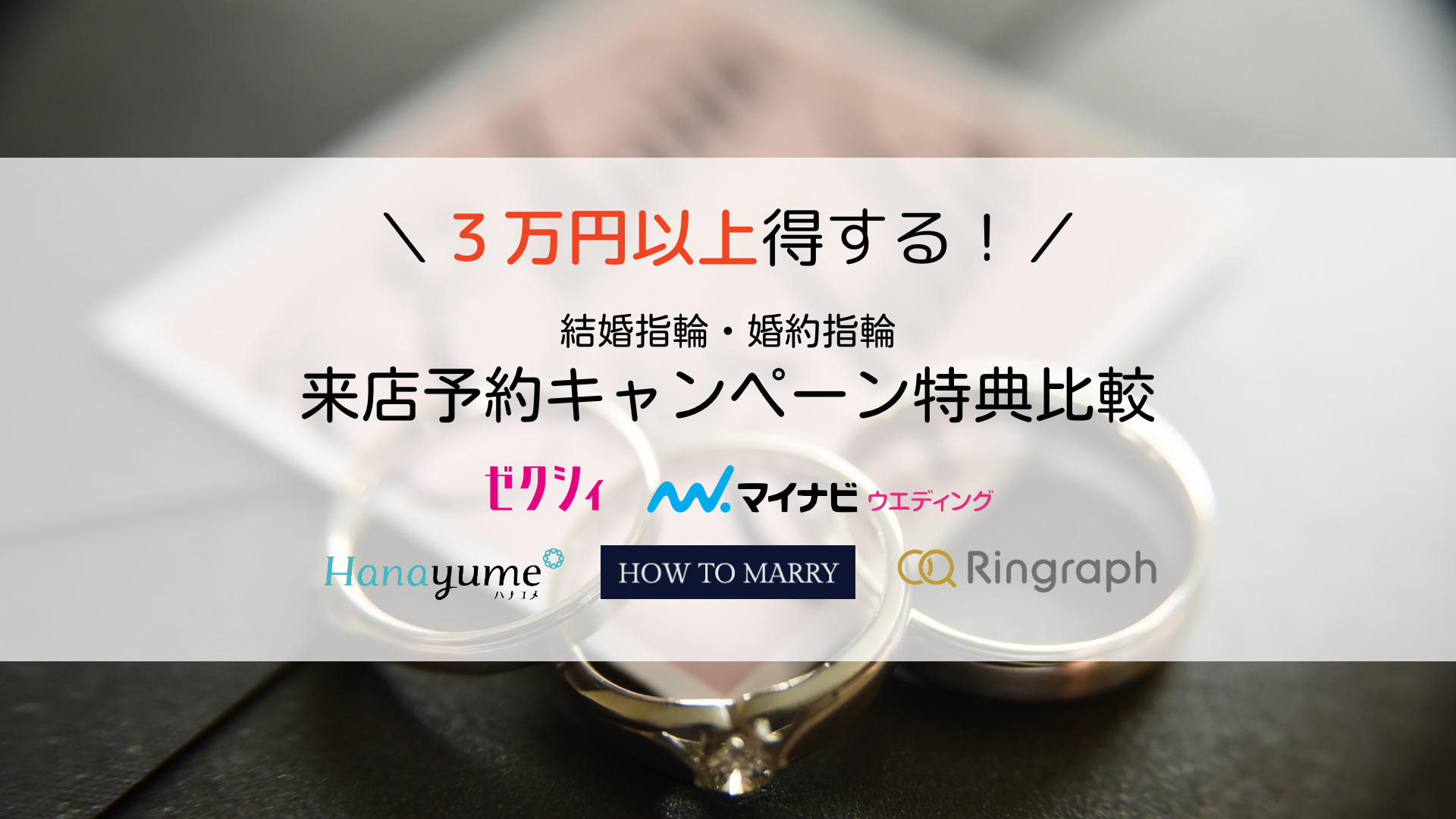日本では縁起物として知られるふくろうですが、海外ではどのような印象を持たれているのでしょうか?
実は中国をはじめとするアジアの国では、かつての風習からフクロウは縁起が悪いとされています。
しかし、アメリカやヨーロッパでは、神話に登場する神様として縁起が良いとされています。
これからフクロウをプレゼントしようか迷っている方に向けて、ふくろうが海外で縁起が悪いとされる理由や、日本では縁起物とされる理由をお伝えします。
相手の国の文化をよく知ることで、失敗しないプレゼント選びをしましょう。
中国でふくろうが縁起悪いとされる理由
死骸をさらして小鳥を脅す風習があった
かつての中国では、冬至や夏至にふくろうの死骸を木の上にさらして小鳥を脅す習慣がありました。
そのため「邪悪の象徴」として、ふくろうは縁起が悪いものとされていました。
ふくろうは漢字で「梟」と書きます。
梟は「木」の上に「鳥」の略体から成っていますが、これは昔の中国でふくろうを木に張り付けにしていた風習が由来です。
ギリシア人は梟の眼に印象づけられたが、中国人は樹上にとまっていることに強い印象を持った。この漢字が鳥部ではなく木部だということを,今回調べてみて初めて知った。
中国では、梟は親鳥をも喰う不孝鳥。日本語フクロウは「チチクラフ・ハハクラフ」に由来との説もある。 pic.twitter.com/ec3aX6lEXC— TOMITA_Akio (@Prokoptas) June 15, 2020
母親を食べる不幸な鳥という伝承
また、古代中国では母親を食べる不幸な鳥という伝承があります。
(※実際はフクロウが母親を食べる習性はないので、完全な誤りです)
春秋戦国時代に書かれた書物「戦国策」にその一説があり、中国ではふくろうは不孝の鳥という印象が古来からあったことが伺えます。
戦国策-Wikipedia
中国の方へのプレゼントは避ける
現在の中国では昔ほど縁起悪いという印象はないでのすが、現代でも昔の名残が残っている地方もあります。
中国の方への贈り物には、フクロウを選ぶのは避けた方が無難です。
もし動物モチーフのプレゼントを贈りたいなら、日本と同じく「招き猫」であれば中国でも幸福を呼ぶと言われているので、とても喜ばれます。
海外でのふくろうの意味
海外の国には様々ふくろうの言い伝えがあり、国ごとで持たれている印象は様々です。
大きく2つに分けると、以下のようになります。
- 幸運の象徴、神聖なイメージ・・・アメリカ、ヨーロッパ
- 不吉な印象、縁起が悪い・・・アジア、アフリカ、オセアニア
アメリカではふくろうはポジティブな意味
| アメリカ | 予言能力がある。危機を避ける |
| メキシコ | フクロウは北風を作り、南風は蝶によって作られると言われている。黄泉の国の使いとも呼ばれていた。フクロウは生者の世界と死者の世界の間を行き来する。 |
| 中南米 | 家内安全、家や家族の守護の象徴 |
アメリカ大陸では、フクロウは主にポジティブなイメージを持たれています。
ヨーロッパと同じく神話が浸透しているため、特殊な能力を持った動物として捉えられています。
アジアではフクロウはネガティブなイメージ
| インド | 発作の子供がフクロウの目のスープで治るという話がある。ヒンドゥーの女神ラクシュミーはフクロウに乗って家々をまわり幸運をもたらすと言われている。 |
| スリランカ | フクロウはコウモリと結婚している。 |
| モンゴル | 埋葬人は悪霊を追い払うためにフクロウの皮をつるす。 |
| 内モンゴル | フクロウは夜家の中に入り人間の爪を収集する。 |
| アフガニスタン | フクロウは人間に火をおこすための鉄と火打石を与え、お返しに人間はフクロウに羽毛を与えたと言われている。 |
| イラン | 不幸を運んで来ると言われている。 |
アジアでは、残念ながらフクロウはネガティブなイメージに捉えられている地域が多いです。
ただ、インドだけは幸運なイメージでと考えられており、女神ラクシュミーが梟に乗って家々を回って幸福を運ぶと言われていることから、神様の乗りものというイメージが強いです。
ヨーロッパでは知識の神として神聖なイメージ
| ヨーロッパ全域 | 博学・博識を表し、知恵と賢明な指導者 |
| スウェーデン | フクロウは魔女に関係する。 |
| フランス | ワインの名産地ボルドーではフクロウの呪いを避けるため、火に塩を投げ入れる。 ブルターニュ地方では、収穫に向かう途中で見たフクロウは豊作のしるし。 |
| イギリス | ウェールズ地方では妊娠している女性が夜フクロウの鳴き声を聞くと、生まれてくる子が祝福されるという言い伝えがある。 |
ヨーロッパでは、ギリシャ神話に登場する知恵を司る神「アテナ」の使い・化身がフクロウと言われています。
そのため、聖なる鳥、知恵の象徴とされ、神聖なイメージがあります。
なお、アテナは別名ミネルヴァとも呼ばれており、同じくフクロウのモチーフが使われています。

ミネルヴァ像の足元にいるフクロウ 引用:wikipedia
アフリカでは魔女や妖術師の仲間として不吉の象徴
| 東アフリカ | スワヒリ族のあいだでフクロウは子供に病をもたらすと言われている。 |
| 南部アフリカ | ズールーの人びとのあいだでフクロウは妖術師の鳥として知られている。 |
| 西アフリカ | フクロウは妖術師の使者。鳴き声は不吉なことの前触れ。 |
| マダガスカル | フクロウは魔女の仲間であり、夜になると墓の上で魔女たちと踊る。 |
アフリカでは、梟は魔女や妖術師の仲間とされており、不吉の象徴とされています。
オセアニアでもネガティブなイメージが強い
| ニュージーランド | マオリの人びとにとってフクロウは不吉な鳥。 |
| オーストラリア | アボリジニの人々にとって、フクロウは女性の魂の象徴。 男性の魂の象徴はコウモリ。 |
| サモア | フクロウはヒトの祖先。 |
| マレー半島 | フクロウは新生児を食べると言われている。 |
オセアニアでは地域によって印象が分かれるところですが、どちらかと言えばネガティブなイメージが強いです。
日本でフクロウの縁起が良い4つの理由
日本でのフクロウは、
- 漢字の当て字(福老など)
- 身体的特徴(首が回る、夜目が効く)
- スピリチュアルなサイン
- ギリシャ神話の聖なるイメージ
から、縁起の良い象徴とされています。
不苦労などの縁起の良い当て字
| 不苦労 | 苦労をしない、苦労を払いのける |
| 不苦老 | 苦労なしに歳を重ねる |
| 福老、富来老 | 幸せに年をとる、豊かに年をとる |
| 福郎、福来朗 | 福が来る人 |
| 福籠 | 福が籠にたくさんつまる |
| 福路 | 旅の幸福、人生の幸福 |
| 袋 | 知恵袋 |
このように、良い印象のたくさんの当て字があります。
風水やスピリチュアルでも、ふくろうは縁起が良いものをして知られています。
夜行性で夜目が利く
夜行性のふくろうは大きな瞳があり、夜でも物がはっきりと見えます。
そのため、「世間に明るい」「見通しが明るい」とされています
さらに、暗闇の中でも小さな獲物を見逃さないことから「幸運を見逃さない」、
捕らえた獲物は鋭い爪でしっかり掴んで離さないことから「手に入れた幸運を離さない」とされています。
また聴覚も大変優れており、畑を荒らすネズミやモグラなどの害獣を獲ってくれます。
そのため、農家の間では昔から益鳥として大切にされており、「悪いものを寄せつけない魔除け」とされることもあります。
首がよく回るので金運アップの象徴に
ふくろうの首は左右270°回ることで有名です。
「首が回る」ことから「借金で首が回らないのを防ぐ」となり、商売繁盛や金運アップの象徴として、縁起の良いイメージを持たれています。
フクロウ鳴き声はスピリチュアルなサイン
鳥が鳴き声は、「幸運の知らせ」と言われています。
フクロウはメッセージを運ぶ役割があり「あなたは守られています」というスピリチュアルなメッセージを伝えてくれます。
フクロウの鳴き声は、神様や天使からの「あなたの願いが叶うまであと少しだから、がんばって!」というスピリチュアルなサインです。
という意味になります。
音もなく舞い降りるフクロウに気付くためには、静かに心を落ち着かせることが大切です。
もし夜の森でフクロウを見かけたのなら、立ち止まってフクロウからのスピリチュアルなサインに耳を傾けてみましょう。
女神アテネの使い・知恵や戦略の象徴
ギリシャ神話に登場する女神アテネの使いとしてフクロウが登場します。
(ローマ神話では女神ミネルヴァの使いとして)
女神の肩には梟がとまっていることから、森の賢者と呼ばれることもあります。
アテナやミネルヴァは知恵・工業・戦略などを司る神なので、お供のふくろうにも同じようなご利益があると信じられています。
女神の加護を受けることで「頭が良くなる」「勝負事に強くなる」と言われています。
まとめ
- 中国ではフクロウは不吉な動物とされており、縁起が悪い
- 日本では幸運の象徴とされており、縁起が良い
- 海外の各国でも印象が分かれ、良い意味ばかりではない
ふくろうのモチーフは日本では幸運の象徴ですが、海外の方に贈り物をする際は配慮した方が良いでしょう。